|
���p��ڂ�web�}�K�W�� �W����r���[11/8-11/11 �ɂēW�]���������܂���
�W����r���[11/8-11/11 �ɂēW�]���������܂���
www.dnp.co.jp/artscape/
���p���C�^�[�̏���
�������ɃC���^�r���[���������܂����B���� ���������^�c����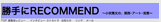 �C���^�r���[�y�[�W�ɂČf�ڂ���Ă��܂�
�C���^�r���[�y�[�W�ɂČf�ڂ���Ă��܂�
www.recommend.ecnet.jp
�I�����C���A�[�g�}�K�W�� �ɓW�]���������܂��� �ɓW�]���������܂���
www.art-yuran.jp/
�@
�@
Artist Statement
2019.June�@
���́A�}���ł���
�Â��Ȃ������F�̏c���̓X���܂����ā@�����Ƃ܂������@�ڂ����킭�@�Ԃ������̐Ԃ��������������Ă������݂��Ă����@�������ւ����Ă��������ā@���ꂪ���������@�Ԃ͎~�܂�@���̐[�����ӂ�����������������ā@�������Ă����@�����������̂��x���Ă�@����������ĊK�i���������Ă�������܂��@�ق��Ƃ���@�O���[�̓��ɔ����������܂ɔ����c���������
�
���������Ă���ЂƂ̃C���[�W����肽��
�
���̂����ɗ����Ă��������̏d�������i�́A����֊s�Ǝ������̂��������F��
���ׂ̗ɂ���ɉ����A���ł���������
�@
2007.Sep�@
��������}�ɗ������Ȃ��Ă����̂�
�v���Ԃ��35�����炢��������⓹��������B
�Èł̒�������̂́A�����̒��𐮂��邱�Ƃ��ł���B
�f���o���A��������B
�Ƃɂ����I��������l�ߍ��߂Ή��������܂�Ă���̂ł͂Ȃ����H
�Ɗ�����B
�ȑO�ɕ��������ɁA�����������i�B
�ނ����������čL����O���[�̐��A�����ǂ̐Ԃ������A���̒��A����3�̉~���A���̒�����˂��h����悤�Ȕ������B
���悤�Ƃ��������Ɍ����Ȃ����o�A�߂Â����Ƃ��������ɉ�������L���B
�O�̂߂�ɕ����čs�������B
���Ȃ葧���ꂽ
��������Ă����@�����₽������
�͔̂M������
���傤�ǒH�蒅����
�@
2007.Feb
Between the scene and the form 07 �Ɍ�����
��̏ォ�猩���鉡�����Ђ낪�锒���B�܂������A�W���W���Ƃ������Ă���B
��������Ȃ��牺���Ă����c
�́�����ւƐi�ނ悤�Ɏw�����Ă����B
�l�p�ɂ���̂́A�������������������B���̏���������߂���������B
���̉��̐����B�������^�I���B�w�������P���x���������B
�����Ƃ����Ɖ�����c
���炳��̔����x�[�W���̌������ɂ́A�₯�ɐԂ��������A�����[�̗���̑O�ɗ����Ă���B
�@
2006.Nov
�� �˗��W dangle�Ɍ�����
�܂�����Ȃ����������̓`�����ŁA�݂Ȃ������^���ƌ��邩�ۂ����܂�ł��낤�B�i�����j���鏗������������͋P���𑝂��A�܂��ʂ̏�������Ό�����������Ɖ����Ă��܂��B�^�삪�����ł���悤�ɐ^�����܂����ڂ�₷���B
�A�[�V�����EK�E���O�B�����w�ł̍���x���
���A�����ɂ���������Ɗ�����R�X���@
�P���悤�ȉ��F��
�ڂɔ�э���ł���M���M�������̎R��
�[���ɂ����̂������ΐF�̊C��
���킢�炵���Ԃ��|�X�g��
�����ɂ���S���I�Ȏ��Ԃ̒��ŏu�Ԃɐ��܂ꑱ��������ł���B
����Ȃɂ��s����őf���炵���l�̈ӎ���
���ɕ����悤�ȃU���U���������o���ɕ`���Ă��܂��B
�@
2006.Apr
�A�[�g�E�E�F�n�[�X -21���I�G��̏d�w��-�Ɍ�����
�@���N���܂��n�܂�A���͂�4���ƂȂ��Ă��܂��܂����B
�u���̌������������J�ˁv�ƁA�������N�����������������́A�K���s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��U���ʼn������ɁA�����������Ė����s���Ă���͂������ɁA����ƋC�����n���ł��B�L�����N�O�ɂł������̌����́A���̖͂ƂĂ��������܂��Ԃ����������炫�܂���B���Ԍ��q�����Ȃ������ł́A������̘b�u���̊ԁA�_�ˋ�`�ɍs���c�v���Ȃ���A����4�{���邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�I�����W�F�̃u�C�������ԊC�������āA����������������H�ꂪ���������Ɍ����邻�̌����́A�����ɍ��ꂽ�Ő��L��Ɛ��Ԍn����肽���A���������ԃr�I�g�[�v�A�����₷���͂ꂽ���тɂ���Đ������ꂽ���R�ɂȂ�G��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�삩��C�ɂȂ���͌��̌��������̐����H��̕��тɂ́A�Ă���ɑ傫�Ȏ�M�������}���V�����A���F���߂ɑ��锒�����̂Ȃ��l�p�A���Ԃ̎O�p���̂��������̑q�ɁB���̏�ɂ́A��ɑ�����������Ƃ����������y��Ƃ́A�����킵���Ȃ������܂������̓����������ƌ��������L�тĂ��܂��B���̊Ԃ����܁A�����[���ΐF�������D�F�̑D���������X�s�[�h�œ����Ă��܂��B
�����ŁA�H��̋Ɩ��A�����������Ă��܂����B
�����A����7:00���B
�����A���낻�뎄���A���ĕ`���Ȃ��Ắc
�@
2005.Dec
���B�́A�����Ɂs������́t��F�������Ƃ́A�����ɂ���v�f��g�ݍ��킹�������łȂ��A�s������́t��������Ă���A�`�A��������S���I�Ȏ��Ԃ̗���̒��̏u�Ԃɂ����Đ������ꑱ����B
�������A���̈��肵��������ꂽ���A���鑤�́s������́t���s������́t�ł��邱�Ƃ�F�����邱�Ƃ�����ɂȂ�B�s������́t�͞B���ɂȂ�A�s������́t�̈Ӗ��͊ɂȂ�A�s������́t�͒��ۓI�Ȍ`��F�Ƃ��Č��ꒈ�Ԃ���̏�ԂɂȂ�B
�@
2005.Aug
�����s���ꏊ������B�[���O���[���������сA�ɕ����A�������B�����Ĕ�э���ł���_�B
�Ȃ���d�Ȃ���ƌ��B����ł��ĊJ�����̂���B
�����́A�����˂Ȃ�Ȃ��ꏊ�B
����Ȃɂ����Ă���ꏊ�Ȃ̂ɁA�ƂĂ���������������B���������Ă���̂ł͂Ȃ��B
��S���I�Ȏ��Ԃ̗���̒��Ō��Ă���B�s����ȃO���O���Ƃ��镂�������o�B
�S�n�悭������قȂ������o���ɂ��Ă���B
�@
2004
�����ɍ݂�u���v�́A�ł܂�Ƃ��č݂�悤�Ɍ�����B
����́A�ƂĂ����ꂽ���̂ŁA�l�̈ӎ��̒��ł܂��A�ω����Â���B
�����ɍ݂�u���v���A�Ȃ����Ă����B
�u�`�v�́A���x����������邱�Ƃŕ���A�����ƞB���ȉ�ւƕω�����B
���̞B���Ȃ��̂ƂȂ�����́A�`��ς��Č����Ă���B
���̌`�ƂȂ��āA�����Ă���B
���̉�ƂȂ��āA�����ɍ݂�B
�Ȃ����Ă����ƁA���̉�́A�ǂ����ɍ݂�B
���̏ꏊ�́A�`�����ƂŌ����ꏊ�B
�������Ƃ�����ꏊ�B
�`�����ƂŁA�������ƂŁA�B���ɂ��邱�ƂŁA
�����Ɗς邱�Ƃ��g�傳����B
�@
2003.Nov
���̎d���ꂩ��A��鎩�]�Ԃł̓��̂�́A
�����̐F�ō��ꂽ�V�Z����ԗ̌�����Z��A
�O���[�̓d���A�Ԃ��|�[��...........�̒��𐼂֑����Ă����܂��B
����Ȃ���[���̋������ɁA���̃A�X�t�@���g�̏�ɍ����傫�ȃc���c����������Ă��܂����B
����́A�����ɂ��镗�i���畂���Č����܂����B
���i�̐F�≚�ʂ́A����݂��邽�߂̋�ԂɊ������܂����B
���ɗh���Č`��ς��Ȃ���...........
�@
2003.Sep
�C���[�W���q���Ă������m�́A�J�^�`�Ƃ��Ă����ɍ݂�B
���x���Ȃ���ꂽ���m�́A���̃��m�̈Ӗ��͂Ȃ��Ȃ�A�J�^�`�Ƃ��Ă����ɍ݂�B
����炵�������悤�Ƃ���ق�.........
�����������悤�Ƃ���ق�.........
�����Ɛ��m�ɂȂ����Ă������Ƃ���قǞB���ɂȂ��Ă����B
���i�́A�B���ɂȂ������m���ς邱�Ƃ��o����ꏊ�B
�����Ɗς邱�Ƃ��g�傳����ꏊ�B
�@
2002.Sep
������Ђɏo���鎞�ɏ��d�Ԃ́A��ɉ����ĊC�������đ����Ă����܂��B
���鏋�����ɂ��̐�ƊC�̋��ڂō�����ȉO���O���Ɛ����X�s�[�h�ŃO���[�H�ꂪ��������
�������������̒�����ł��܂����B
�����ƌ��Ă���Ƃ��̉�ɂ́A�����H���������悤�Ɏv���܂����B�i���Ȃ̂��ȁH�j
���^���Ƃǂ߂Ă��炸�A�������{�[�Ƃ��āA�ǂ����֊s�Ȃ̂��킩��Ȃ��܂܁E�E�E
|